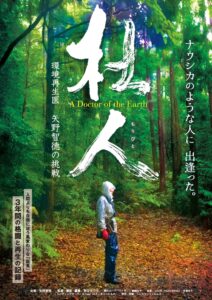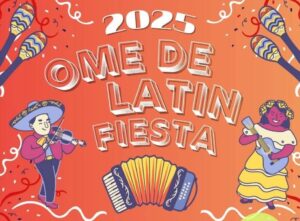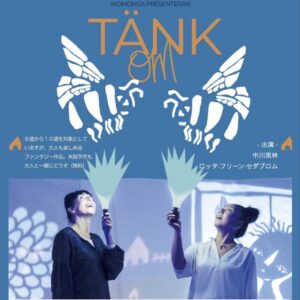食は”命の保障”、農業は”未来の命の保障”
子ども達に残せるものは何か?
子どもが産まれてからずっと考えていたことです。

私の結論は、お金よりも何よりも子ども達に残したかったもの、それは「食」でした。
食の選択ができる環境と食の安全。
体験畑(やなぴ畑)を始めたかった理由の1つでもあります。
オーガニック体験畑|instagram

私たちの身体は食事で得た食べ物でできていて、その食べ物を作ってくれる人達がいて、そこには豊かな土壌があります。
今、その食環境が大きく変わろうとしています。
食の海外依存が高まり、日本の食料自給率は先進国の中でも低く、わずか37%。
農家さんの高齢化が進み、離農する方も増えてきています。
もし、輸入がストップしたら?
このまま農業を辞めざるを得ない状態が進んだら?
これからの私たちの食はどうなってしまうのでしょう?
子ども達に健全な「食環境」を残すことができるのでしょうか?
食と農の未来を一緒に考えてみませんか?
私たちが変わることできっと未来は変えることができます。
未来への種まきしていきましょう。
お子様連れでも大丈夫!騒いでしまってもお子様ルームに移動してお子さんと一緒にお聞きいただけます。
※同伴のお子様(0歳~中学生)は参加費無料
ぜひお誘い合わせの上、会場までお越し下さい。関係者一同、心よりお待ちしております。
パネリスト・主催
■鈴木宣弘 教授(東京大学 農学博士)
三重県志摩市出身。東京大学農学部卒。農林水産省、九州大学農学部教授等を経て2006年9月から東京大学大学院農学生命科学研究所教授。国民のいのちの源である「食」と「農」の価値を訴え続けている。著書にベストセラー『農業消滅』(平凡社新書)がある。
https://www.ga.a.utokyo.ac.jp/p_suzuki.html
■柳川貴嗣(ヤナガワファーム)
東京都青梅市出身。法政大学社会学部卒業。専攻は環境社会学。2013年に有機JAS認証を取得。生ゴミ堆肥による農業から環境問題へのアプローチを実践し農業からの循環型社会を目指す。ヤナガワファーム代表。(株)東京有機農家代表取締役。有機認証協会JASCERT公平性委員。
持続可能な未来の農業「ヤナガワファーム」 | OMEGOCOTI
■石川敏之(あきる野市・ゆっくり農縁)
自然栽培のゆっくり農縁えん長。映画上映プランナー。
生協を早期退職後、市民活動やナマケモノ倶楽部などに関わりながら、食と農と在り方の未来に向けた活動をしている。
https://www.facebook.com/slownouen/
■主催:青梅の農業を考える会
代表 柳川 貴嗣(有機農家ヤナガワファーム)
青梅の農業を考える会 | Facebook
パネリストからのメッセージ映像
柳川貴嗣(ヤナガワファーム)
鈴木宣弘 教授(東京大学 農学博士)
お話会終了後、ヤナガワファームをはじめとする地元農家さんによる地元農家さんの野菜販売もございます。
新鮮野菜が揃うのはもちろん、消費者が農家さんと直接会話できる機会です。
| イベント詳細 | |
|---|---|
| 開催日時 | 2022/5/21(土)13:00-15:30 |
| 場 所 | ネッツたまぐーセンター(文化交流センター)・多目的ホール 東京都青梅市上町374番 |
| 参加費 | 大人 ¥2000、高校生~大学生 ¥500(当日集金) |
| 定 員 | 100名 |
| 駐車場 | 提携有料駐車場あり |
| お申込み | 申込専用ページ |
| お問い合わせ | non1004@live.jp |
| URL | Facebookページ 青梅の農業を考える会 |
『便利で豊かな社会と引き換えにしたもの』
産業革命以降、文明の発展や便利さと引き換えに私たち人類が手にしたものは、二度と元に戻すことのできない未来への傷跡です。
私たちは化石燃料を使い、豊かな森、水、土などのありとあらゆる資源の消費を加速させ、私たちの生活は「便利」で「豊か」とされているものになりました。その生活はとても甘美なもので、それにより私たちは地球からもらったものを地球に返すということを忘れてしまいました。
まるで何かに取り憑かれたように消費を続け、いつの間にか消費することから逃げられなくなってしまったかのようです。
この私たちの営みは地球を、森を、水を、土を、私たちの生活や健康を、そして未来を生きる人たちの命を少しずつ蝕み始めています。
しかし、それに気付きながらも、私たちは化石燃料を、豊かな資源の消費を、止めることはできません。魅了的な消費社会は私たちに一体何を残してくれたのでしょうか。
私たちは一体どこへ向かうのでしょうか。もう戻れないかもしれないというところまで来てしまったのでしょうか。
『日本の食糧と農業の現状を知って欲しい』
農業という仕事は自然の中で行われる産業です。ですから、自然環境の異変にとても敏感なのです。
新型コロナに始まり、ウクライナの情勢、終わりの見えないこれらの社会への不都合は、日本の食糧事情に大きな影響を与えます。
100%に近い数字で肥料や種、穀類や家畜用の飼料を海外に依存している日本は、その過度な海外依存による脆弱性が露呈されてしまいました。
温室効果ガスに由来する気候変動は季節感をなくしてしまい、今まで作れていた野菜を作れなくしてしまいました。
合理的な土地利用という名目で土壌は減り続ける一方で、規制やしきたりといった制約により、たくさんの新規就農者たちが苦しい経営に追い込まれ、果ては離農という結末を迎えることも少なくありません。
それに伴い農家は高齢化し、耕作放棄地は年々増え続けています。
私は農業を生業とする者として、かつてない程に逼迫した危機感を覚えました。環境問題、農業の危機、これらの問題は一見するとそれぞれ別の問題のように見えますが、本質的な部分での構造は、全くと言っていいほど同じ様相を呈しています。
『食は命の保障、農地は未来の命の保障』
食べることは「命」保障そのものです。
農地を残すことは未来の「命」の保障でもあるのです。農家だけが農業を考えればいいのではありません。
地球上で生きる命すべてが考えなければならない課題です。
そこで、まずは身近なところから、自分の住んでいるまちで、自分のこととして考えて欲しい。
その思いでこの会を立ち上げました。
『食と農業の未来を一緒に考えましょう』
そして、この会の立ち上げに伴い、東京大学大学院農学生命科学研究科教授の、鈴木宣弘先生にご講演を頂くこととなりました。
第一部では揺れる世界情勢の中で日本の食糧事情はどうなってしまうのか。
日本の農業の抱える課題と解決方法をお話し頂きます。
第二部ではそれを受けて、青梅市ではどのような課題と可能性があるのか。
鈴木先生と青梅市の有機農家の柳川貴嗣のパネルディスカッションとなります。
未来のためのお話しを、学生や子育て世代の方にも分かりやすく解説していきます。
是非ご参加下さい。
青梅の農業を考える会
代表 柳川 貴嗣(有機農家ヤナガワファーム)
青梅の農業を考える会 | Facebook